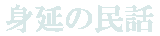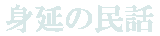【地区】
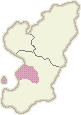
旧身延町
身延地区
【ジャンル】

動物
【キーワード】

歌や呪文・言葉の遊び
|
| 【出典】 『富士川谷物語』 (加藤為夫、山梨日日新聞社 1987) |
てうちてち
てうちてち
|
昔、身延村梅平(うめだいら)の甚左衛門(じんざえもん)という若者が、遠くから大豆(だいず)の種を手に入れてきて、山尾根(やまおね)の畑にまきつけた。これが、このあたりの大豆栽培(さいばい)の起こりである。
粟(あわ)、ヒエより、自然に弱い作物なので、上手(じょうず)に作れるまでに数年かかった。大豆は味が良く、実入(みい)り時、夜、狸(たぬき)や猪(いのしし)に食い荒らされ、これを追い払うのがひと仕事だった。
ある晩(ばん)、甚左衛門が、大豆畑のそばの小屋で「寝ずの番」をしていて、つい、うとうとした時、開け放しの小屋の戸間口へ、一匹の狸がやってきて「豆尾根(まめおね)の甚どんが、豆食って、てうちてち、てうちてち」とからかった。
ハッと目をさました甚左衛門が、すかさず「おまえこそ、てうちてち、てうちてち、てうちてち」と早口でやり返した。狸は負けじと早口で「甚どんは、てうちてち、てうちてち、てう……」と言ったが、三つめの「てうちてち」で舌がもつれ、舌をかみ切って死んでしまった。
「てうちてち」とは、狸の鳴き声である。
豆尾根の地名は、現在、「豆うね」に変わっている。江戸時代、身延ではこの甚左衛門の家を代々つぐものだけが、大豆で豆腐(とうふ)を作る権利を持っていた。この家系は、今も続いている。
|
もどる
|